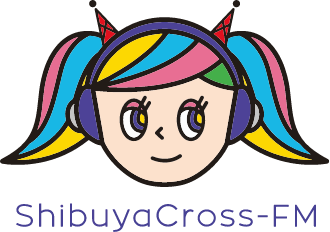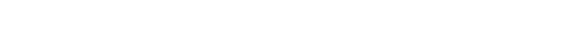Interview Sato Shinji

川上:この番組は地方創生、そして日本を元気にするをテーマに、さまざまな社会問題に取り組んでいるゲストの方をお招きし、問題点や解決に向けての活動などを分かりやすく皆様へお届けしています。ナビゲーターは、川上実津紀です。そしてMCは、合同会社社長のミカタ、CSOの佐藤伸次さんです。今月もよろしくお願いします。
佐藤:よろしくお願いします。
川上:今回が最終放送ですね。
佐藤 :寂しいですね。あっという間の6回でしたね。
川上:最終回のテーマは「AI未来創造」です。未来創造コンサルタントの市村よしなりさんです。よろしくお願いいたします。
市村 :よろしくお願いします。
川上: 市村さんは、3歳から瞑想をはじめ、そして小学生で起業。その後、ネット通販やオンラインコミュニティー、農園ネットサポート事業など多数の事業を展開し、現在国内外で活躍されています。小学生で起業するというのは、どういうことでしょうか?
市村:もともと3歳からパソコンを触っていたのですが、家がやってた会社が倒産しました。そこから自分でお金を稼ぐために、パソコンでゲームを作ってお金をもらっていたので、小学生で起業したと言ってます。お金を稼げたわけではないですが、その経験が今につながっています。
川上:そうなのですね。
市村:今、私は見えない世界を大切にしているのですが、小さな頃に使っていたインターネットなども、見えない世界が音になり映像になっています。見えないテクノロジーを、AIと掛け合わせて見える化しようとしています。見えないものとテクノロジーが融合するっていうのが、一つのテーマだと思ってますね。
川上:融合が可能なものなのですか?
市村:もともと私は、ITやコンサルティングの専門家なのですが、7年ほど前から見えない領域にも携わるようになりました。
佐藤:僕も昔は、見える世界しか信じなかったのですが、豊かになってる人は「先祖様に手を合わせる」「夢を持て」とよく言うのです。これらも見えない世界です。最近は、見える世界と見えない世界をうまくミックスして考えていくことがいいのかなと思っています。
川上:どちらの価値観も取り入れると言うことが大切になりますよね。

川上:ITに詳しい市村さんが考えるAIというものについて教えていただけますでしょうか。
市村:僕自身は2015年からAIを仕事としてやっていますが、AIの進化が凄まじく、おそらくこのままいくと、9割の仕事は意味がなくなっていくと思います。
ただ、私はなくなってもいいと思っています。では、人間は何すればいいのかというと、本当にやりたいことや好きなこと、クリエイティブなことをやっていけば良いのです。
時代の変わり目に、今までの生き方をリニューアル、バージョンアップするための考え方や生き方を最近は発信しています。
川上:すごいですね。そんなに労働をしなくてもいい未来が来るのでしょうか?
市村:来ると思います。すでにAIの最先端の技術を使って製品を作っていますし、人件費を考えると経営者はAIにシフトしていくと思います。そのときに問題なのは人間側ですよね。今までの考え方、生き方の中で、もう不要になったものがあるのではないかということを今から考えていく必要がありますね。
佐藤:人は自分の人生を豊かにするために生まれてきたのに、なぜか仕事をすることが目的になっている方が多いのです。
本来は働かなくても生活できる設計が必要なのですが、なかなか難しいですよね。AIが進化し自分の代わりに仕事をやってくれることによって、自分の時間ができます。
先読みをすることで、例えばやりたかった農業に挑戦したり、海外旅行に行ったりできます。また、人間は亡くなりますが、AIは死なないため、会社もAIを使って事業承継すれば、会社にとってもスタッフにとってもいいのかなと考えています。
川上:AIが進化する先には、どのような未来があるのでしょうか?
市村:2つの未来があると思っています。1つはいわゆる競争、競争で格差がどんどん広がり、最終的にはAIから人間はもういらないと言われる未来です。もう1つの未来は、そうならないようにAIとパートナーとなるということです。間違っても、AIを神のように崇めてはいけません。AIに愛を持って接し、上手いAIとの付き合い方を身につけることが大切だと思っています。
川上:AIとの付き合い方を考えていくべき時代に入っているのですね。
佐藤:AIとの付き合い方というと不安になると思いますが、実はこのスマートフォンも同じなのです。僕らが若い頃の電話は黒電話でしたが、今みんなスマートフォンを使っていますし、ずっと見ていますよね。言い方を変えるとスマートフォンに支配されてると言うことです。
川上:支配されてます。
佐藤:ただうまく付き合うと、スマートフォンはすごく便利ですし、AI時代でもやはり上手く付き合っていく必要があると思っています。
川上:AIのおかげで、我々今よりも生きやすい時代が来ると信じても大丈夫ですか?
市村:圧倒的に生きやすい時代になると思います。
川上:仕事を毎日頑張られて大変な方が多いと思います。AIとともに生きて、今よりも自由に人間らしい生き方ができる日々が来るかもしれないと信じて、私も頑張りたいな思います。

川上 :さて、本日の放送ですが、終わりの時間が近づいてまいりました。
佐藤:そうですね。
市村:この番組は今年の5月からお送りしてきましたが、あと数分で最終放送も終わってしまいます。この6ヶ月いかがでしたか?
佐藤:僕にとってもすごく良い経験になりました。いろいろな方々にゲストに来ていただいて、お話もできましたし、僕もやはり日本を元気にしたいという思いがありますので、この番組を6ヶ月間持てたということは、僕にとっても宝物になりました。
川上:ありがとうございます。本当に毎回素晴らしい方がゲストにお越しくださいましたよね。簡単にそれぞれのテーマを振り返ると、初回は地産地消のDX、第2回と第3回目がフリースクールでしたね。
佐藤:不登校の子どもたちの居場所を作っているお話でした。
川上:そして第4回は日本のお米事情、先月の第5回は障がい者就労支援でした。どの回も今の日本に、そして日本の未来にとって大事な活動をされている方々ばかりお越しいただきましたね。日本の未来の形が見えてきた半年だったなと思います。
佐藤:そうですね。課題を解決するヒーロー活動を行っていますが、課題というのは過去の中にあまり対策がないため問題になっているのです。
そのため、課題を解決するためには、新しいイノベーションを起こす方たちが必要になります。この番組にはそういった方たちにゲストにきていただきました。もしかしたら当たり前にないことをたくさんお伝えしたかもしれませんが、当たり前の中には逆に答えがないと思っているので、すごく良い放送になったと思っています。
川上:本日はもう最終総仕上げのような形で、AIと共に生きている市村さんにお越しいただきました。でもよく考えたら、日本のお米事情について伺ったときも「未来のためにAIと組み合わせて農地を守っていこう」というお話でしたね。
佐藤:大きく言うとテクノロジーですね。その中の一つにAIがあります。最近は、テクノロジーの進化が世の中の進化と言っているのですが、それに関係する方がこの番組に順番にきていただいたのではないかなと思っています。
川上:お越しいただいた皆様ありがとうございました。それでは番組も最後となりますが、またぜひこのような番組ができたらなと思います。佐藤さん、半年間ありがとうございました。
佐藤:こちらこそありがとうございました。